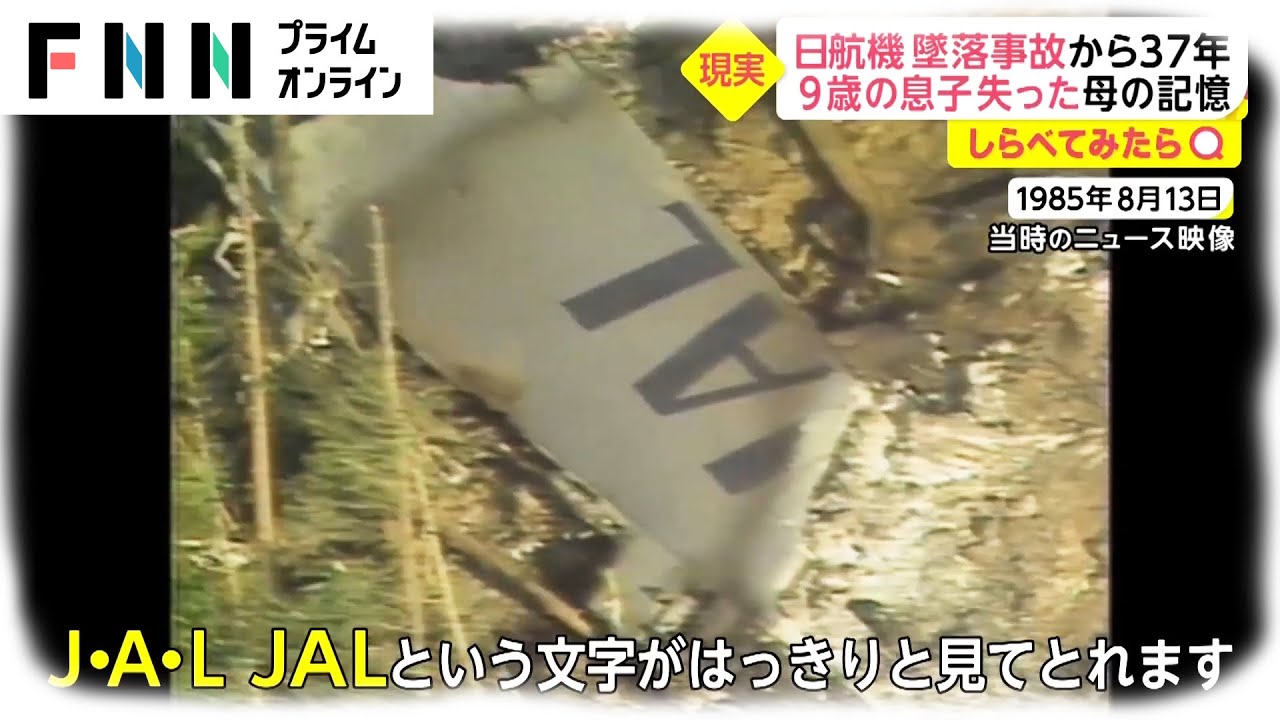
【しらべてみたら】日航機墜落事故から37年 ボイスレコーダーに残された”生死かけた闘い”
1985年8月12日、日本航空123便の墜落事故から37年が経過しました。この事故は、日本の航空史上最悪の事故として知られ、520人の命が失われ、生存者はわずか4人という悲劇的な結果をもたらしました。事故が発生したのは、群馬県上野村の御巣鷹の尾根で、当時5204人の乗客と乗員が搭乗していました。 今年6月、御巣鷹の尾根で新たに発見された酸素マスクが、事故の記憶を新たに呼び起こしました。37年が経過した今でも、現場には当時の傷跡が残っており、事故の影響は遺族たちの心にも深く刻まれています。事故で9歳の息子を失った美谷島邦子さんは、37年間この場所に登り続け、息子の思いを胸に刻んでいます。 事故当日、123便は羽田空港を出発し、大阪行きの空の旅を始めました。しかし、離陸からわずか12分後、相模湾上空で異変が発生しました。機内の圧力隔壁が破損し、客室の空気が尾翼に流れ込み、機体の制御が失われました。この状況下で、操縦士たちは生死をかけた戦いを繰り広げることとなります。 高浜機長、佐佐木副操縦士、福田航空機関士の3人は、必死に操縦を試みましたが、機体は激しい横揺れを起こし、制御不能の状態に陥りました。乗客の中には、この恐怖の中で必死にメモを残した人もおり、彼らの想いが記録されています。「死ぬかもしれない。みんな元気で暮らしてください」といった言葉が、乗客たちの心情を物語っています。 墜落の瞬間、機体は急降下を始め、最終的には御巣鷹の山々に激突しました。事故調査委員会の報告によれば、原因は1978年の事故時に行われた圧力隔壁の修理ミスとされています。この事故の影響は、航空業界全体における安全性向上のきっかけとなり、以降、国内での旅客機墜落事故は発生していません。 現在、遺族たちは事故を風化させないために、記憶を語り継ぐ活動を続けています。谷口町子さんは、夫のために特別な作品を制作し、彼の思い出を大切にしています。日本航空安全啓発センターでは、墜落した123便の残骸が保管され、次の世代に伝えられています。 37年後、事故の記憶は消えることなく、遺族たちの心に生き続けています。彼らは、再び同じ悲劇が繰り返されないよう、未来に向けての教訓を伝え続けています。
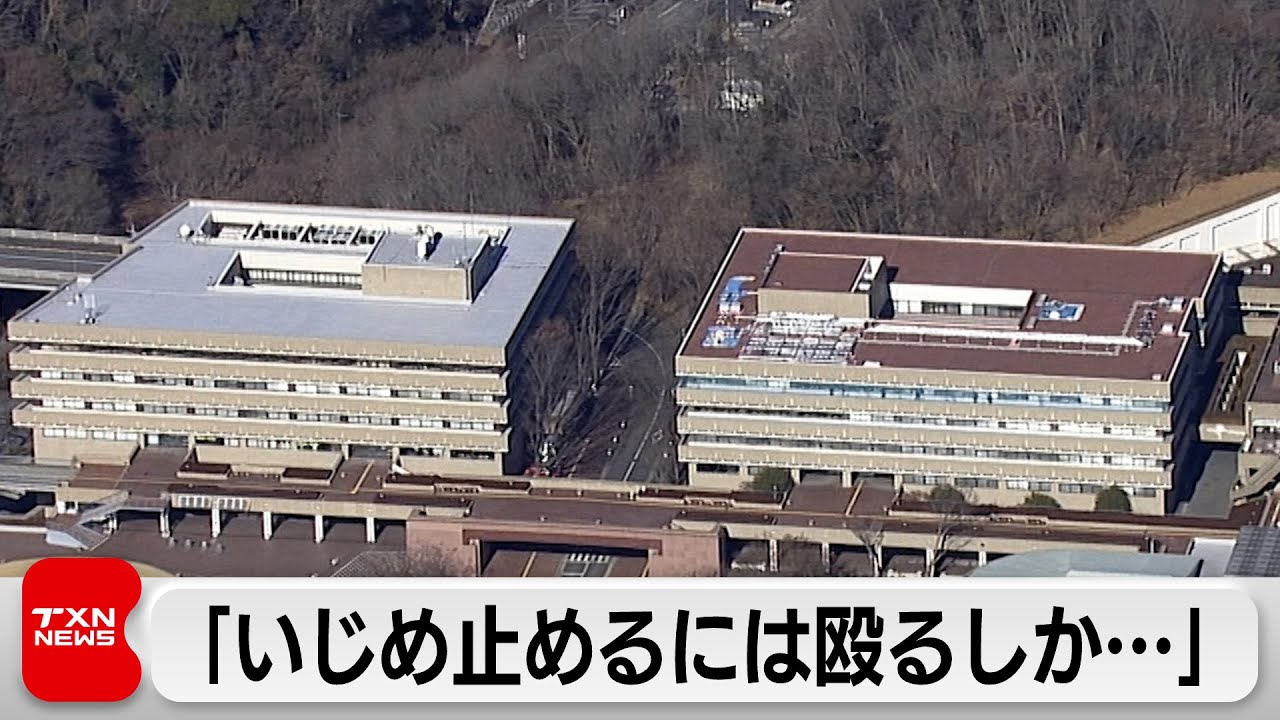
法政大ハンマー襲撃 「いじめを止めるには殴るしか」
法政大ハンマー襲撃 「いじめを止めるには殴るしか」 東京都町田市にある法政大学多摩キャンパスで、授業中に女子大学生がハンマーで同級生を襲撃し、8人が怪我をする事件が発生しました。逮捕されたのは、法政大学社会学部2年の韓国籍、ユ・ジヒョン容疑者(仮名)で、事件は昨日午後4時前に起こりました。警視庁によると、ユ容疑者は教室内で20代の男子学生をハンマーで殴り、障害の疑いで現行犯逮捕されました。 怪我をした学生は、法政大学に通う8人であり、その中にはユ容疑者が面識のある学生が2人含まれていましたが、その他の学生については面識がないとされているようです。警視庁の調べによると、ユ容疑者は日頃からいじめを受けていたと感じており、「いじめを止めるには、学生たちを殴るしか解決方法がない」と話していることが明らかになりました。 この事件は、いじめの問題についての議論を呼び起こしています。いじめを受けていたというユ容疑者の主張は、彼女が取った極端な行動の背景にある心理状態を示唆しています。警視庁は、ユ容疑者と被害者の学生との間に何らかのトラブルが存在したと考え、引き続き調査を進めています。 法政大学側は、学生の安全を最優先に考え、今後の対応について慎重に検討しているとしています。また、いじめ問題に対する学校の取り組みや、学生間のコミュニケーションの重要性が改めて問われる事態となっています。 このような事例は、単なる個人の問題に留まらず、社会全体の教育環境や人間関係にまで影響を及ぼす可能性があります。今後、いじめの根絶に向けた具体的な対策が求められるでしょう。

“帆”で燃費向上・脱炭素…洋上風力発電…国内外で注目 商船三井と長崎県が連携協定
商船三井と長崎県が連携協定を締結し、洋上風力発電や省エネ技術の開発に取り組むことが発表されました。この協定は、県内の造船業界の新たな展開を促進し、環境に優しい技術の進化を目指すものです。 長崎県には、船の建造や修理を行う59社の造船企業が存在し、さらに設計や部品供給を行う関連企業も数百社に上ります。造船業は県の基幹産業として、輸出額は1300億円以上に達し、県の経済に大きく寄与しています。そこで、県は商船三井との連携を通じて、環境配慮型の船舶開発を進めることを決定しました。 商船三井は、世界的な海運企業であり、昨年度の売上高は1兆2600億円を超えています。今回の協定では、二酸化炭素の排出量を削減するための新技術の研究開発が中心となっています。特に、洋上風力発電を利用した再生可能エネルギー分野での協力が期待されています。大島造船所は、この協定により新たなビジネスチャンスが生まれることを期待しており、これまで商船三井と10年以上にわたり共同研究を行ってきました。 注目すべきは、大島造船所が開発した「ウインドチャレンジャー」という特殊な帆です。この帆は、最大で53メートルの高さまで広がり、風向きや風力を感知して調整する機能を持っています。この技術により、船の燃費が向上し、航路によっては最大で8%の二酸化炭素排出量の削減が見込まれています。 このような省エネ技術は国内外で注目を集めており、実用化が進めば関連産業に広がる経済波及効果が期待されます。今回の製造に関与した企業は10社以上に上り、地元の産業との連携が強化されています。長崎県は、この協定が新たな省エネ技術の創出のきっかけになることを願っています。 さらに、商船三井は、風力や火力といった再生可能エネルギー分野でのノウハウを活用し、海に浮かぶ構造物を用いた付帯式発電の開発にも力を入れる考えです。県内の造船関連企業にとって、これらの新たな技術への参入は大きなチャンスとなるでしょう。 長崎県と商船三井の連携協定は、造船業界だけでなく、船舶に関わるすべての企業にとっても新たな成長のきっかけとなることが期待されます。これからの取り組みを通じて、県内企業の活性化が進むことに注目です。